高校入試が終わり新たな道へ
1月(和歌山私立)、2月(大阪私立・公立特別選抜)、3月(公立一般入試)と続いた高校受験も無事終了しました。これまでの、ご家族はじめ周りの方々の深いご協力と熱いご支援に心より感謝申し上げます。

それぞれ自分の進む道が決まりました。
高校に入学した後は、新たな環境の中で新しい仲間、新しい目標が見つかると思います。悩んだり、喜んだり、それも将来の糧にして、充実した高校生活が送れますよう心よりお祈りいたします。
(講師一同)
1月(和歌山私立)、2月(大阪私立・公立特別選抜)、3月(公立一般入試)と続いた高校受験も無事終了しました。これまでの、ご家族はじめ周りの方々の深いご協力と熱いご支援に心より感謝申し上げます。

それぞれ自分の進む道が決まりました。
高校に入学した後は、新たな環境の中で新しい仲間、新しい目標が見つかると思います。悩んだり、喜んだり、それも将来の糧にして、充実した高校生活が送れますよう心よりお祈りいたします。
(講師一同)
1月末、2月10日に行われた和歌山、大阪の私立高校入試。
塾生、ともに全員合格しました。今まで頑張ってきた努力が実りました。
専願の人は、これで高校内定の切符を得たことになります。4月の新学期が始まるまで、気分はゆっくりできますが、学力を落とさないように、しっかりと高校への準備をしておいてください。

併願の人は、まだこれから本番の公立入試が控えています。第1志望合格目指して、あとひと頑張りです。最後まで精一杯、頑張り続けてください。
がんばれ、受験生!
(教務部)
本日の「おもしろ実験教室」は、最も人気のある実験のひとつ、「スライムづくり」です。
まず、スライムを作り、その性質や状態を考える実験です。スライムとは固体と液体の性質をともに持つ物質で、入れる容器によって形が変幻自在になり、手で触れることもできます。そのスライムにいろいろな色を付けると、カラフルスライムの完成です。子どもたちは大喜び。


次に、砂鉄を加え「砂鉄スライム」にチャレンジです。
これは不思議!磁石を近づけると、くっつきに来ようとして不思議な動きをしようとします。子どもたちの表情に驚きが!
手で触れ、自分で体験することで興味が膨らみ「なぜ?」「どうして?」と感じることが大切です。
(教務部)
1月中旬の私立中学入試も無事終了しました。

受験予定がすべて終わり、それぞれの進路が決まりました。おかげ様で、塾生みんな、合格を勝ち取ることができました。学校の勉強内容に比べてはるかに難しい勉強を頑張り続けた彼らに拍手です。そして、ご家族の方々はじめ温かく励まし、支えていただいた周りの方々に厚く御礼申し上げます。
これから先、それぞれ進む道において大きな幸運と成功をお祈りいたします。
(職員一同)
旧年中は、本学園に何かと深いご理解ご協力を賜りましてありがとうございます。
昨年は、ここ数年続いたコロナ禍が5類対応になり、社会が大きく変化しました。社会活動においても、あらゆる方面でようやく動きが感じられるようになりました。

子どもたちを取り巻く環境にとって、このコロナ禍は大きな意味を持っています。学習形態の変化に伴い、学習への関わり方も様変わりしました。2020年からの小学教科書、2021年からの中学教科書の改訂の時期と重なり、大なり小なり子供たちの学習を直撃しました。コロナ禍前とコロナ禍後では、著しく教育環境が異なります。子供の少子化という社会的背景がある中で、個の重視、多様性の尊重の意味がより大きくなってきています。同時に、柔軟性、創造性、発想力、対応力など「個の力」のウエートが重要視されます。根本にあるのは、知識であり思考力であり、その習得と表現です。多様化された時代に、子どもたちが迷わず進んでいけるように私たちは、温かく見守り、力強く導き、後を押していかなければなりません。そのためにも職員一同、全力で子どもたちに接していく所存です。
今年も本学園に温かいご理解、ご支援を宜しくお願い申し上げます。
2024年元旦
栄 光 学 園
11月3日、毎年恒例(年2回)の「全国統一小学生テスト」が当会場にて行われました。小学生は、中学受験のための業者模試を会場に受けに行く受験生を除くと、通常、学校以外で実力テストを受ける機会はまずありません。だからこそ、貴重な体験です。


全国レベルの学力テストを受けることによって、現在の自分の位置、学習の理解度や課題を客観的に知ることができます。全国の順位、偏差値のみでなく、都道府県別や男女別のデータもわかります。そして何より、各教科の分野別理解度も分析され、今後の学習の参考材料になります。
(教務部)
受験生、保護者対象の公立高校及び私立中学・高校の合同進学説明会が10月29日、泉大津の「テクスピア大阪」で開催されました。年々変わりゆく入試制度や各学校の特色、進学実績、学校生活など、学校の進路に関わる先生方と、直接会って話を聞くことができる機会は貴重です。また、志望校がまだはっきりと決まっておらず、迷っている受験生にとって、多くの有意義な情報を得て自分の進むべき道を見つける絶好のチャンスです。




当日は、公立高校の「入試説明会」と個別ブースによる説明会、私立校の相談ブースを設け、約80校の進路担当の先生からお話を聞きました。2部構成にして来場者の分散対策を取りながらも、会場は、約1300人もの真剣な表情の受験生たちと保護者の方々の熱気に溢れていました。
(教務部)
本日、準会場である本学園にて、今年度第2回目の英語検定が実施されました。塾生だけでなく、一般の方たちも多く参加されました。検定試験は、相手との競争ではなく、自分の学習習熟度を見るもので、各目標級合格を目指します。普段からの学習方法や理解度を過去問などで確認しながら臨むと効果的です。
また、受験生にとっては、検定結果が入試に有利になる優遇措置も年々取られるようになり、入学金免除や本番の得点との比較換算や加点など受験の負担が少なからず軽減されるメリットもあります。最近では、中学受験においても、入試科目に英語を選択できる学校もあります。
ますます進む「英語力」需要。これだけグローバルになった社会で、多国語を身につけるのが必須の時代がまもなくやってくるかもしれません。
2025年度から、現在の準2級と2級との間に新たな級が新設される予定です。 (教務部)
いよいよ待望の夏です。
1学期も残りわずかになり、もう少しで夏休み突入です。
暑い夏、熱い夏。
期末テストも終わり、部活も忙しくなります。
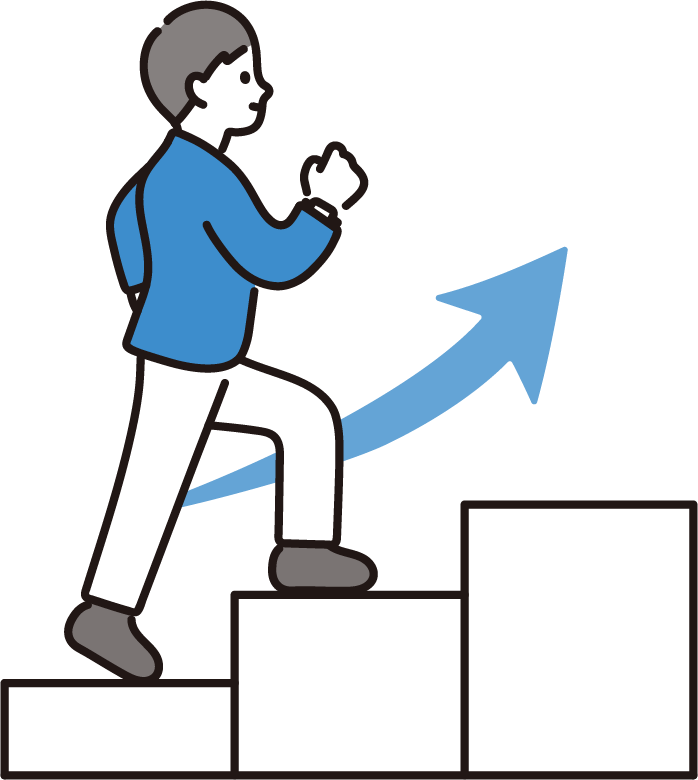
「四分位範囲と箱ひげ図」「反例」「累積度数」(数学)、「仮定法」「現在完了進行形」「原型不定詞」(英語)、「イオン化傾向」「ダニエル電池」(理科)などなど、少し前までは高校内容だったものが中学に移行されています。指導要領の改訂から、小学校は4年目に、中学校は3年目になりましたが、かつての教科書の内容と、質・量ともはっきりと違います。受験前に慌てて頑張っても取り返すのは至難の業です。もし少しでも1学期につまづきを感じたら、そして前年度のことに不安を感じたら、この夏休みは、追いつき追い越す“盛り返しの夏”にしてください!
(鈴木)
先日実施の「全国統一小学生テスト」の問題の見直し会を行いました。
つい受けっぱなしにしてしまいがちなテストですが、どんな問題でも見直し、やり直しは必要です。当日、どうしても解けなかった問題が、やり直してみると解き方が急に浮かんできたり、ヒントをもらうと、「あっ、なるほど…」となったり。


どんな試験でも、受ける際の大切な必須事項は準備、対策です。本番では、時間配分、問題を解く優先順位、ミスや書き間違いがないかのチェック、そして集中力の維持など、定められた時間内で消化していかなければなりません。試験終了後は何よりも、見直し、やり直しなどの復習が大事です。次回のために備えること、同じような問題を次の機会には解けるようになることが、実力アップの最大の方法です。地道な努力が結局は、大きく前進する近道になります。
(鈴木)
2007年11月に「さあ、競争だ!」というフレーズとともにスタートした四谷大塚主催「全国統一小学生テスト」も今年6月4日で、17年目の32回を迎えました。
年2回実施される同テストをこれまで受験した人数は、延べ360万人を超えます。前回の昨年11月の受験者は、約14万6千人になり、全国47都道府県の2600もの会場で行われる「日本最大の無料公開学力テスト」といえます。
詳細なデータをもとに、現在の理解度、全体の中での自分の位置が全国規模だけでなく、都道府県別にも知ることができます。
初めて参加した人は、次回も受験する人が多く、今まで複数回受けた人が多いです。前回との成績の比較ができ、今後の学習の対策に役立つ資料とモチベーションにもなります。
次回予定は、11月3日です。
(鈴木)
文科省は、17日、全国の公立中学校と高校などを対象にした2022年度「英語教育実施状況調査」結果を発表しました。政府が目標とする水準の英語力を持つ生徒の割合は、中3で49.2%(英検3級相当以上)、高3で48.7%(英検準2級以上)。政府は22年度までに「50%以上」を目標としてきましたが、中3、高3ともわずかに届きませんでした。
大阪府では、中3で49.1%、高3で50.8%でした。

本日、今年度第1回英語検定が準会場である本学園にて実施されました。多くの受検生の人たちが、日ごろからの学習の成果を発揮すべく、真剣な表情で試験に臨んでいました。
当会場で受けられた人の二次試験(3級以上)は、7月9日予定です。
(鈴木)
新年度になって最初の定期テストです。試験範囲がほぼ一週間前に発表されて「さあ、テスト勉強だ」と気合十分です。普段の授業で習った内容、プリント、ワークから出題される定期テスト。限られた時間をどれだけ有効に、要領よく使って勉強するかが大きなポイントです。
中1の皆さんは、初めて中学校の定期テストに臨むわけですから、小学校とは違い自分の「管理力」が試されます。期日までの提出物は必ず仕上げなければなりませんし、暗記量もかなり増えます。苦手な科目、単元は特に時間をかけて、ただ教科書を見るだけでは得点が難しいのが中学校のテストです。「中1の最初のテストって、簡単でしょ」いえいえ、教科書改訂に伴い、質・量ともなかなかの内容です。今始まったばかりの中学生活。試行錯誤をしながら自分の勉強法を見つけていってください。
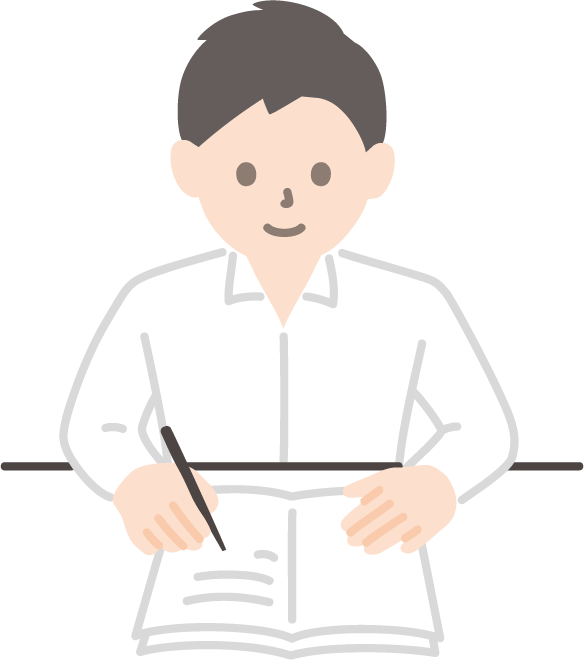
直前の日曜日には、塾の授業以外にたっぷりと予想問題に取り組んでもらっています。「できたよ。」「同じような問題が出たよ。」はうれしい声。「せっかく塾でやったのに、あ、飛んじゃった」は残念!
またひと月もすれば、期末テストが来ます。子供たちは勉強に部活にとても忙しいです。
中学生活は今、始まったばかり。頑張ってください。
(鈴木)